人を好きになるとは、とても簡単だ。
「――ふぅ」
黒髪の女性は、陶磁器のような黒い腕で頬を撫でた。血の通わない無機質な感触が、暑いこの日は心地よい。
兎に角、胸が痛いようだ。痛いらしい。曖昧。
思いついたようにすっくと立ち上がり、投げ捨て気味に置かれた箒を手に取った。
「掃除……たまにはまじめにしよう」
巫女服姿の女性――霧崎沙娜は陰鬱な表情で呟いた。
日の光は眩しい。御神木の陰にはなっているが、木漏れ日がちらちらと目の端を掠める。鬱陶しいことこの上ない。
「……はぁ」
溜息。これで何度目だろう、と沙娜は反芻し、止めた。切りがないから。それほどまでに、胸の内が重い。
それもこれも現代日本の所為なのだ。問題を大きくすり替え、何と残酷だろうと沙娜は大げさに嘆く。
境内には誰もいない。誰か来ることすら滅多にない。そんな場所を掃除するという、無意味さ、虚無感が胸の内を抉る。
そう、この行為には何の意味もないのだ。
そしてそれは、ある意味では素晴らしいことである。
「…………はぁあ」
より一層重い溜息がでた。自分に呆れ、箒を地面にポトリと落とす。自分自身もつられて、地面に伏せた気分になる。
「何で……好きになっちゃうかなぁ」
頭を掻き毟った。右腕では上手くできない。もどかしい。
沙娜の頭の中には、一人の女性が居ただろう。赤茶けた髪、死んだような紫の目、少々猫背気味だが背は高い。そんな女性。
振り払う。消え失せろと、無慈悲に。
叶わないのだ。女性同士とか、そういう問題もあるだろう。だがそれだけではないことは、本能的に分かる。
近づくと愛おしいのに、近づくと後悔するのだ。
「……そんなことなら」
――好きにならなければ良かったのだ。
後悔先に立たずとはよく言うものである。後悔する時には全てが遅い。
苦しむぐらいなら、愛おしくて憎いなら、殺してしまいたい程に愛が深いなら。
あゞ、この胸裂いてしんでしまえ。紅い着物はさぞ美しかろう。
「どうかこの世が夢でありますように」
目を閉じて、木の洞に落ちる。そこは彼の化け物の住処か。零の狭間に巣食う、意思を持たぬ阿弥陀籤。
「危ないよ、そんな所で寝ると」
歯噛み。血が出るほどに。白い口元に朱が灯る。
どうしてこいつはいつもいつも。都合が良いのか。私が望んだのだろうか。そうか、私は。
「帰って」
「どうした急に」
「今は、独りが良いから」
「奇遇、私も。座ってさ、那由多の小説でも読んでる」
「……勝手に、どうぞ。私は掃除するから」
「サボり巫女さんが珍しく殊勝な。終わったら水羊羹買ってよ」
「嫌」
――どうしても、この人を嫌いになれない。
きっとこの苦しさは、螺旋の如く続くのだろう。あゞ神はなんと残酷な事よ。
願わくば、この夢が醒めますよう――そして現実は幸せでありますよう、柄にもなく願います。
「夢ね」
「現実」
「雅が無いわね」
「科学者ですから」
――または、この夢が掬われますよう。


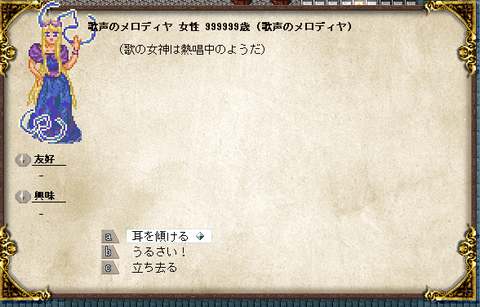
コメント